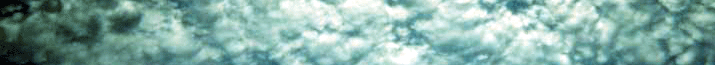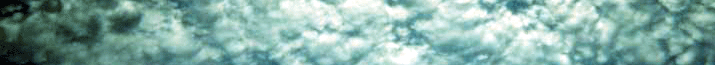 背中からはじまる
背中からはじまる
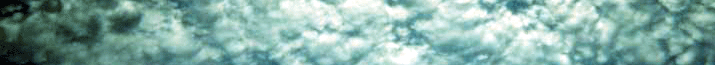 背中からはじまる
背中からはじまる
|
彼女の姿を見るのは今回で二度目だった。 一度目に彼女の後姿に目を奪われ、二度目には既に恋に落ちていた。 いや、一度目に既に恋に落ちていたのだがそれに気付いたのは二度目の時だった、という方が正しいような気もする。 田中理菜、その名を知ったのは三度目に彼女の姿を見た時だった。
一度目は入学式の時だった。 今思えばスーツ姿の彼女の背中、何の変哲の無い姿だったと思う。 他の新入生でほとんど席が埋まっていて講堂は保護者や新入生、マイクテストの声、色々な音が混じりあった中にその後ろ姿を見つけた。 自分でもよく分からない、吸い寄せられるようにそこ一点に視線が向かった。 とりあわけ背も高く無く、スーツも黒、髪もショートで少し明るめの茶色。 街を歩いていてもたまに居る目で追いたくなるような、とても目立つような顔立ちでもなく、身長でもなく、でも何故か道行くすれ違う人々の視線を集める人間。 そんな表現が一番似ているだろう。 だが、彼女の後姿は私だけに有効だった。 彼女は背中だけで私を虜にした。
二度目は玄関ホールで彼女とすれ違った。 遠くからやってくる彼女の姿を目で認めると視線を送っているのを気付かれてはいけないという気持から私の目は宙を泳いでいただろうと今になって思う。 逆にそれが自然だったのか不自然だったのか、自分でも分からない。 だが、心臓がいつもと違う動きをしている、早くも無く遅くも無く。 もしかしたらいつもと同じなのかもしれないが、この時は心臓の動きを頭の片隅で意識していたのは確かだった。 友達数人と談笑しつつ私の方に向かってくる。 わざとピントを外した目の片隅で彼女の私服姿を拝みながらすれ違う。 見てはいけないという気持ちからか鞄を持っていた手からとても熱と汗が噴き出てくるのを感じた。 彼女たちとすれ違い、声が遠くに聞こえるのを感じながら振り向いた。 すると彼女の姿はもう見えなかった。 校舎の柱の影になっていて見る事が出来なかった。 先ほどまでピントは合っていなくても明るかった視界にフィルターがかかったように少し彩度が落ちた。 その時、これは彼女に対する恋心なのかもしれないと確信では無いがそれに近いものを認めた。
三度目はとある授業だった。 先生が最初の授業という事で学科ごとに一人ひとり自己紹介をするというものだった。 名前と簡単な自己紹介、他学科と一緒に受ける授業は日に何回も無い。 学科、学籍番号順に座っていたので彼女の番を待ちわびた。 順番に一人ずつ思い思いに好きな事を述べてゆく。 私はどちらかと前に出たりするのが苦手な方で普段だとこのような自己紹介をしなければいけない事を呪っただろう。 だが今回はこの自己紹介を企画した先生に少しだけ感謝した。 彼女の方を堂々と見る事が出来、そして名前を知る事が出来る。 二度目の玄関ホールですれ違った時に友達に「リナ」と呼ばれているのを知った。 だんだんと彼女の順番が近付くにつれまるで自分の番かのように胸が高鳴る。 「田中理菜、好きな事は音楽鑑賞です。宜しくお願いします」 席を立ち自己紹介をし、軽く頭を下げ、着席する。 その一連の流れはとてもゆっくりと、そして壊れたテープのようにずっとずっと彼女の台詞が繰り返された。 「田中理菜、田中理菜、田中理菜」 彼女の肉声は落ち着き少し掠れの入ったプリンの底の甘苦いカラメルソースのようだった。
あの声で私の名前を呼んでもらったらどんなに幸せなのだろう。 その願いが叶うかどうかは全く分からない。 始まったばかりの学生生活。 その間に彼女と親しくなれたらいいと思った。 後姿を追うだけではなく面と向かうことが出来ればと思った。 休講の時に二人で喫茶に入り他愛の無いお喋りをして時間をつぶすなんて事が出来たら何て幸せだろう。 四度目に彼女に出会った時、今日は暑いですねなんて会話を夢の中で練習しながらまた明日学校に向かうのだ。
|
『背中からはじまる』2009.4.20
Copyright・ 2009 Urakawa All rights reserved.
top