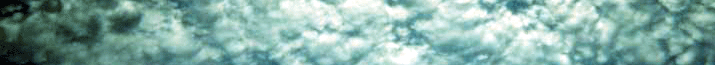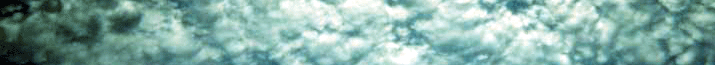 夕日の中の沈黙
夕日の中の沈黙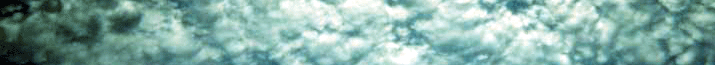 夕日の中の沈黙
夕日の中の沈黙| ガラッ・・・ 「おーい! もう下校時刻過ぎてるぞ! 二人とも、早く帰れよ!」 ドアが開いたと同時に、繋いだ手を伝わって明子の肩が少し揺れたのを感じた。 「はーい! すみませーん! もうすぐ帰りまーす!」 そう明子がドアへ向かって明るく普段より一回り高い作り声で元気に答えた。 廊下の足音がだんだん遠退いていくのと同時に、再び沈黙が訪れた。 赤く染まった教室の中は静けさだけが残り、明子の熱が再び私の腕に伝わった。 「ねぇ、もう学校閉まっちゃうから、帰りながら話・・・しよ? ね?」 その明子の声は先程先生に向かって発せられた声とは異なり、弱々しかった。 私は声にならない声で「うん」と呟き、頭を縦に振った。 教室を出て、廊下を進んで、下駄箱に着くまで明子は私の手を離さなかった。 まだ、明子と手を握っているような感覚が残っている。 手は、私は、明子の温かい手を欲していた。 日も落ちていた事もあり、学校から延びている道に人影は疎らだった。 「さっき言った事、ね・・・高校に入ってからずっと思ってた」 黒く大きく聳える門を二人同時に潜る。 私は校外へ踏み出すと同時に止まっていた話を続けた。 「明子が告白されるのを待ってる度、誰かに明子を獲られちゃうんじゃないかって・・・」 世界は赤く染まり、足元には長い影が出来ていた。 その時、一緒に踏み出そうとしていた足が動きを止めた。 振り返ると、明子の大きな目から白い頬までつうっと一本の線が伝っていた。 私は驚いた。 今まで、明子の笑顔は何千回と見てきた。 だが、5年間一緒に居て泣き顔は一度も見た事は無かった。 明子を泣かせてしまったという事実と同時に夕日の赤がその泣き顔の美しさを演出していた。 「あき・・・こ?」 触れたら壊れてしまうのではないのかと言う不安に見舞われながら、私は明子へとゆっくり一歩を踏み出す。 頬を伝っていた涙は明子の目から留まることなく溢れていた。 私はポケットからハンカチを取り出し、明子の頬へ添えた。 明子の手がハンカチを押さえた私の手に伸びた。 重なる手は再びお互いの熱を伝える。 「私・・・唯にそんな風に思われてるなんて考えてなかった」 明子の口の動きが声と同時に重なる手へと伝わる。 頬へ伝わる涙は、ハンカチをじんわりと湿らす。 「私は、明子ともっと一緒に居たい・・・ただ、それだけ・・・」 目の前に居る明子の潤んだ目を見つめながら私の思いを口にする。 明子と夕日が重なる。 学校の外の通りに人影は見当たらなかった。 ふと思い出したかのように風が明子の髪を肩から流す。 「私も、唯に言わなきゃいけない事があるの」 そう言いながら明子は私の手からハンカチを取り涙を拭った。 拭き終わると同時に、明子はふっと一度大きく肩で息をした。 「私にとって唯は世界で一番大切だから!」 一瞬、何を言われたのか分からなかった。 一番欲している言葉を、夢に描いていた言葉が好きな人から――明子の声になって耳に伝わる。 「もしかしたら男の人が唯の代わりになるかもと思ってきたんだけど、いつも告白の場面になると唯の事が頭を過ぎってたの」 そう続ける明子の足はゆっくりと駅に向かっていた。 私も急いで向き直り、明子の後ろを追う。 しゃんと美しい背筋はいつもの明子を窺わせる。 「だから、気付いたんだ。さっき唯に言われた事で私と同じ思いだったんじゃないかって」 夕日を背負いながら、二人同じ速度でゆっくりと歩く。 明子の顔を横目にちらと見る。 赤く染まった空のせいか明子の頬も赤みを帯びていた。 「誰にも唯の代わりにはなれないし、代わりなんて要らない。私には・・・唯が居るから」 お互いがお互いを必要としていた。 気付いていないのは自分たちだった。 少し触れた手が、迷わず同時に合わさる。 手のひらから手のひらへと熱が伝わる。 さっき繋いでいた時よりも何倍も熱かった。 夕日に二人の影が長くのびる。 その影は、長く長く、触れ合ったまま続いていく。 |