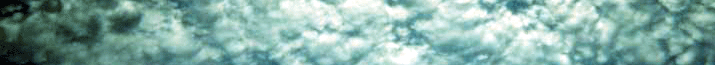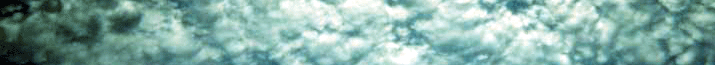 キスに残る
キスに残る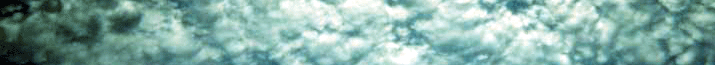 キスに残る
キスに残る| カタカタ・・・夜のオフィスにキーボードを打つ音が響く。 「あー、もう! 何でこんな時間まで資料整理なんかしなきゃいけないの!」 バサッと書類の束を机の上に投げ捨てながら、千枝が叫ぶ。 退社間際に部長から言い渡された仕事がまだ終わらないよう。 「まだそっちはいい方だよ? 私なんてこの企画書の締め切り明日なんだからねー」 千枝の声に応えるように私も愚痴をこぼす。 椅子に身を委ね、腕をぶらりと垂らす。 長時間使いっぱなしで疲れている手と目を少し休める。 机の上にあるコーヒーを手に取る。 退社時刻に皆が帰宅するのを見ながら入れたので、既に冷め切っていた。 冷たいコーヒーを飲み、千枝の方を見る。 無量に積まれた机の上の資料は一向に減る気配を見せなかった。 叫びたくなるのも頷けた。 千枝と視線が合う。 「部長も言うの遅いと思わない? ねぇ、香奈」 「うん・・・そうだね」 私はそれだけしか言えなかった。 この部署は誰もが知っている。 千枝は、部長のお気に入りだと言う事を。 きっと気付いていないのは千枝だけだ。 今日、部長は退社間際に仕事を言い渡し、オフィスに残った千枝を口説こうと考えていたのだろう。 それでなければ、特別急がない資料の整理など頼む理由も無い。 私のただの勘繰りかもしれない・・・。 でも、それだけ千枝に寄って来る男に対して過敏になっていた。 そんな理由で、家でも出来る仕事を夜の9時にオフィスでしている私は馬鹿なのかもしれない。 馬鹿でもいい。好きな人と長い時間居られるなら、何でもいい。 「ねぇ、コーヒーもう冷めてるんじゃない? 淹れなおそうか?」 千枝がいつの間にか隣に立っていた。 私の冷たいコーヒーを触ってそう言った。 少しだけ触れた指で微かに千枝熱りを感じる。 「うん、お願い」 私の返事を聞くなり千枝は給湯室の方へ歩いて行った。 夜のオフィスにはぽつぽつとしか明かりがついていない。 外のネオンがとても眩しく、人のざわめきも時折耳に入る。 この街のどこかで部長も居るはずだ。 社長に無理矢理連れて行かれたお酒の席で彼はめいっぱいの作り笑いと苦笑いの狭間でお酌をしているのだろう。 そんな想像をしながら、私は心の中で抱腹絶倒する。 運が悪い人・・・少し同情心を抱きながら、またキーボードを打つのを再開した。 夜のオフィスにリズムよくカタカタと音が響く。 「はい、香奈。コーヒーどうぞ」 そう言って千枝が差し出したカップからは湯気が立っている。 「ありがとう」 千枝の手からカップをそっと受け取る。 重なる指がコーヒーの熱に負けていたせいか、ひんやり気持ちよかった。 コーヒーと千枝がいつもつけているフレグランスの心地よい香りが良い具合に混じりあたりに漂う。 淹れてくれたコーヒーをコクリと一口飲む。 口の中いっぱいに目の覚めるような苦味が広がる。 苦すぎる・・・千枝の淹れたコーヒーはとても苦い事を忘れていた。 苦味の残る口の中、またパソコンに向かう。 さぁっと寒風が部屋に吹き込む。 思わず、風の吹いてきた方向に目をやる。 窓辺で千枝が煙草を咥え、ライターをポケットから探しているところだった。 「千枝! ここ禁煙でしょ!」 言葉と一緒に、体も動いていた。 千枝の咥えていた煙草を取り上げる。 「窓開けてるから大丈夫だよ」 そう言って、千枝が私の手から煙草を取る。 外のネオンが視界の中で揺らぐ。 千枝と私の髪が風になびく。 風に吹かれて、千枝の甘い匂いがふわりと流れる。 「本当に、煙草・・・吸わないで?」 千枝に向かって問いかける声が潤む。 「うん・・・分かった」 そう言うと、持っていた煙草をそっと箱に戻した。 煙草なんかで身体を駄目になんかして貰いたくない。 千枝を想うと、全てに置いて気が気でない、そんな自分が居る。 パタン、と言う音とともに風が止んだ。 窓が閉じると流れなくなった空気が肩にふわ、と乗った気がした。 相変わらず、カタカタと言う音と書類の重なる音だけが広いオフィスに響く。 一口飲んだコーヒーは既に冷えていた。 カップを置いた隣の携帯に目をやると、もう11時を回ろうとしていた。 「ねぇ、千枝。もう帰らない? もう終電なくなるよ?」 もう仕事もあと少し。 暗さを増したオフィスは流石に不気味だった。 窓に目をやると、街のネオンだけは一層明るく眩しかった。 「えー、まだ資料整理終わってないよー」 机の上に積み上がっている書類に目をやり千枝が嘆息をもらす。 「今日中で無ければいけないものじゃないんだから大丈夫だよ」 部長が千枝に残業をさせる為にやらせた仕事だ。 いつだっていいに決まっている。 「じゃぁ千枝は帰る準備してて。私はカップ洗ってくるから」 そう言って自分の空になったカップと千枝のカップを手に持ち、給湯室へ向かう。 カチャ、と流しへカップを置こうとした手が止まる。 千枝の口紅がカップに写っているのが目に入る。 ふいに千枝の顔が――朱唇が頭に浮かぶ。 その唇に、誘惑に、私が負けてしまった。 目を瞑り、そっと優しく、千枝に触れるようにカップに唇を重ねる。 冷たいカップに対し私の身体は中から温かくなっていく。 カップを置いた後も夢見心地、ここは会社だと言う事をすっかり忘れていた。 「ねぇ、香奈? 帰らないの?」 あまりに遅かったので千枝が心配して呼びに来たのだ。 その一言で目が覚めた。 「ああ、ごめん。帰ろう」 エレベーターがゴウンという音とともに上がってくる。 4,5・・・人の居ない時間のエレベーターは早い。 先程した事を思い出すと、恥ずかしさと疚しさで千枝の顔が見れなかった。 少し寒さを感じ、コートのポケットへ手を入れる。 カサ、と何かが当たる。 数日前に買ったアメをいれていたのを忘れていた。 「千枝、コレあげる。煙草吸うんだったら今度からアメにしてね」 私は千枝にアメを差し出した。 「アメ? ありがとう、ちょっとお腹減ってたんだ」 千枝の手に一つアメを落とす。 アメを口に含んだ時、丁度エレベーターが着いた。 重く開く扉から眩しい光が二人に降り注ぐ。 一階を押し、閉まるボタンを押す。 密室の空間に千枝のフレグランスの香りが広がる。 「あっ! このアメ、果肉入ってる?」 静かなエレベータの中に千枝の声がする。 「うん。入ってるけど、何か駄目だっ・・・」 言葉を言い終わる前に、口が塞がれていた。 視界がぼやけるほど千枝が近かった。 頭の中で疑問符が先程打っていたキーボードのカタカタと言う音とともに並ぶ。 何が起きているのか、一瞬の出来事で事態が飲み込めなかった。 すると、千枝の口の中にあったアメが私の口の中で転がって居る事に気付いた。 「ごめんね、私、果肉駄目なんだよねー」 突然の事態に私の頭はついていけてなかった。 手の甲で頬を撫でると、異常なまでに熱かった。 嬉しさか、熱か分からないまま顔は火照る。 キスの後に残ったアメが現実だと私に気付かせた。 口の中で転がすアメは甘美だった。 エレベーターを下りた後も、千枝の移り香が私を纏っている。 数歩前を歩く千枝が振り返る。 「また、アメ頂戴ね」 次も果肉入りを渡したら?と私の中で誰かが囁いた。 |