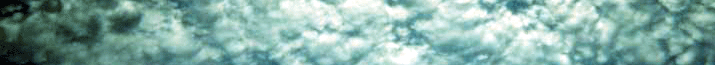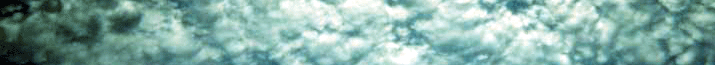 幸せを称える
幸せを称える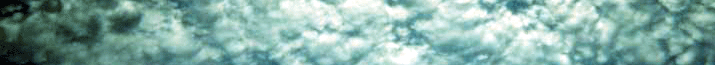 幸せを称える
幸せを称える| 埃臭い。 図書室のドアを手で開けながらそう感じた。 誰も居ない部屋のひんやりと冷たい空気が頬に当たる。 ドアの正面にある窓からは裏庭にある木木の間から微かに光が漏れていた。 グラウンドからは野球部やサッカー部の掛け声が遠くから聞こえる。 「三好さん、やっぱり来ないのかな・・・」 ドアを開けた鍵をカウンターの上に置きながら呟く。 部活へ行っている彼女は今、体育館で練習をしているのだろう。 図書室へ来る前にチラと覗いた体育館で一生懸命にバレーをしている彼女の姿が目に入った。 すらりと伸びた白く綺麗な足、身長も私よりはるかに高い。 どこに居ても美しい彼女は目立っていた。 髪は短いけれど、伸ばしたらきっと絹のように美しいだろう。 きっと図書委員の仕事なんて忘れているのだと思う。 来ないのなら別にいいと思っている。 ただ、彼女と一緒の委員会に入りたかっただけなのだから。 彼女の横に名を列ねれるだけで満足してしまっている。 鍵を置いたカウンターには新しく入った本が重ねてあった。 それをぱらぱらと捲りながら、ゆっくりと仕事に取り掛かった。 「ちょっと休憩しよ・・・」 近くにあった椅子に腰をかける。 新しい本は全て棚に仕舞い終わった。 あとは片付けと図書カードの整理。 流石に二人でする仕事を一人で片付けるのは大変だった。 グラウンドからはまだスポ魂のような掛け声が続いている。 一人でしても、何も楽しくない。 図書委員会に入った頃はただ、羨ましく彼女を眺めているだけで私は満足してた。 今もその感情に満足感を抱いているものの“彼女と同じ部屋に二人だけ”という状況が叶うのではないかという希望を捨ててはいない。 親しくなりたいと思った時期もあった。 だが、親しくなってしまったらその先の嫌われてしまうのではないのかという感情がいつも先に立っていた。 こうして仕事をしている間も、本を一つ一つ棚に戻す間も、頭の中は本ではなく彼女の事だけだった。 実を言うと、彼女に対する想いが憧れなのか、恋愛なのかいまいち自分でも分かっていない。 「大西さん?」 ガチャリと図書室のドアが開く。 少し低めのハスキーボイスが私の名を呼ぶ。 驚いて振り返って見ると、そこには三好さんが立っていた。 バレー部の練習を途中で来たのか、ジャージ姿でドアを閉めていた。 「ごめんね? 図書委員のことすっかり忘れてて、一人で大変だったでしょう?」 憧れ――いや、好きな人が目の前で立っている。 私は椅子から立ち上がり彼女を見上げる。 20センチくらいの身長差、首の筋が張るくらい顔を上げなければ彼女が見れない。 もしかして疲れて夢でも見ているのだろうか? 「仕事どれくらい終わった? もしかして全部済んじゃった?」 いつも近くで聞きたくても聞けなかった声が、すぐ横で発せられる。 教室や体育館で微かに聞こえるハスキーボイス。 耳に快い声、それが私の隣から聞こえてくる。 「大西さん? 聞こえてる?」 そして私の名前を呼び、彼女の白い手が私の肩をぽんと軽く叩く。 「あ! うん! 大丈夫だよ! あと半分くらいだから!」 彼女が私の肩に手を・・・夢ではない。 彼女の手の重みが身体に残っている。 現実であって、その上隣には彼女が居る。 この部屋に居るのは私たち二人だけ・・・そう思うと心中穏やかではいられなかった。 先ほどの返事も声が上擦っていなかっただろうか。 きちんと返事する事が出来ただろうか。 まさか彼女が来るとは思って居なかった。 仕事よりも私の頭の中では心の整理に追われている。 今までの私には考えられないような奇跡のような事態。 「ねえ、大西さん。この本はどこだっけ?」 今、隣に彼女が立っているのは夢でも何でも無い。 「ああ、それはこの奥の棚の2段目」 質問に答えるのが精一杯で、彼女の方は見れない。 こんなに近くにいるのに、遠くでは眺める事が出来たのに。 近くも無く遠くも無く、ただのクラスメイト。 近づき過ぎると一定の距離を保った関係が壊れてしまうのではないのかと不安に駆られる。 「前から思ってたんだけどもしかして、大西さんって私のこと嫌い?」 思いも寄らない言葉が彼女の口から聞こえる。 さばさばしていて人間関係には恬淡な人だと思っていた。 声のする方を見ると、本を両手に抱え真っ直ぐに彼女がこちらを向いていた。 足元を見ると窓の近くに立ってる彼女の影がもう少しで私まで届こうとしている。 ゆらりと影が動く。 彼女の影に私が重なる。 見上げると、彼女が目の前に立っていた。 「三好さんの事、嫌いじゃないよ。どうして?」 大好きなのに、そう口にするのはどうも憚られる。 言いたいけれど言えないジレンマに耐える。 「私、何か避けれられてるのかなぁ・・・って」 私の頭の上から降る声はバレーをしている時に聞こえてくる大音声では無かった。 避けている訳じゃない。 他の子と同じように出来ないのは私のせい。 「避けてないよ? でなければ今日、図書室になんか来てないよ」 そんな口を濁しながら彼女の影から背を向け離れた。 彼女が好きだから図書委員になった。 彼女に会えるかもしれないから、今日この図書室に居る。 好きな人には好きだと言いたい。 でも彼女に伝えれないこの言葉をどうすればいいのだろう。 彼女を見た時から襲われたこの感覚、気持ち、そして迷路に迷い込んでいる私を。 「じゃぁ・・・どうして私の方を見て言ってくれないの?」 背中から声が伝わる。 「ねぇ、大西さん・・・何で?」 彼女の手が私の背中にやさしく触れる。 押すわけでもなく、ただ、そっと指が触れる。 彼女の一部に触れているだけでこれ程までに私は幸せになれるのだと知らなかった。 初めて味わうこの感覚、この時間はしっかり私の今を流れている。 「三好さんが好きだから・・・」 取り返しのつかない一言。 今まで悩んでいた言葉がふっと出た。 出来ない事が出来た達成感と同時に後悔の念が襲ってくる。 彼女の手が動かず、まだ私の背中に触れている。 今、背中にある彼女の手が私にとっては凶器のように思える。 触れ合っている部分に全ての神経が注がれる。 何か他の事を言おうと、そう思っていたのだけど言葉が喉から出てこない。 ただ、ただ、時間だけがゆっくりと流れる。 グラウンドから聞こえてくる声に耳を傾けるが何が聞こえているか全く理解出来ない。 「大西さん・・・今の、本当? 冗談じゃ無くて?」 そう声を掛けられたと同時に背中から彼女の手が離れた。 肌に少し残る重さが私の立たされている状況に現実味を持たせる。 彼女の方を向こうと思っても身体が言う事を聞かない。 前を向いたまま、私は質問の答えを返す。 「本当に、三好さんが好きなの。気持ち悪くてごめんね。女同士でこんな・・・」 その先の言葉が詰まる。 彼女の手が私の肩に回る。 ゆっくりと伝わる、温かい体温。 私の背中と彼女の身体が優しく重なる。 「三好さん?」 何が起こっているのか、この状況こそ夢ではないのか。 彼女の温かさが心地よい。 だが緊張のあまり私の身体が強張っているのが分かる。 「気持ち悪くなんか無いよ。私も大西さんのこと好きだから・・・」 彼女の口から出てきた言葉を疑う。 「三好さんが? 私のことを?」 聞き返さずには居られない。 今、彼女の身体に触れているだけで夢だと思っている。 ただのクラスメイトのはずだった。 彼女と同じ部屋に居る幸せ。 彼女の横に名前があるだけで幸せだった。 「私、大西さんに嫌われてるんだと思ってた。だからその言葉が凄い嬉しい」 彼女のハスキーボイス。 今、その声が全て私に向けて発せられている。 「あの・・・下の名前で呼んでいい?」 彼女の少し照れの入った甘い声が聞こえる。 「うん。私も・・・いい?」 彼女の名前を呼べる日が来るなんて。 私が呼んでもいいのだろうか? そんな不安は幸せに負けている。 「さよ・・・ちゃん」 彼女の声が私の中で何度も木霊する。 私の名前を呼んでもらえる日が来るなんて。 振り返り、彼女の目を見つめる。 背の高い彼女に少しでも近づこうと背伸びする。 「美緒ちゃん」 頭の中で何度も何度も呼んでいた名前。 初めて口に出す幸せ。 「さよちゃん」 「美緒ちゃん」 私たちは見つめ合い、図書室が暗くなるまでお互いの名を呼び続けた。 |