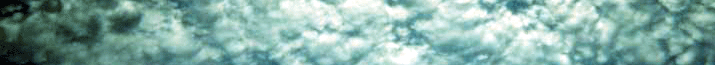 夕日の中の沈黙
夕日の中の沈黙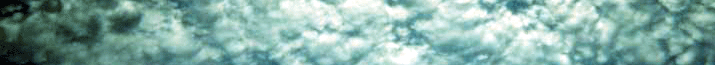 夕日の中の沈黙
夕日の中の沈黙| 「私、また告白されちゃった」 そう言いながら明子が小走りで教室へやって来た。 肩まである少し茶色がかったシルクの様にさらりと肩から落ちる髪。 触れてしまったら自分の力で壊してしまうかも知れないと思えてしまう様なその細い身体。 白く透き通った肌が西側の窓から入る夕日の燃える様な赤を映している。 「ねぇねぇ、唯、聞いてる?」 そう呼びかける明子の顔には溢れんばかりの笑みがこぼれている。 聞いているよ、という意味を込めて私が明子を見上げた。 カタリ、と静かな教室に音が響く。 私の前の席に明子は座った。 放課後、下校が近づいてきた時間に二人きりで教室に居た。 人が少ない教室は、それはもう静かだった。 昼間の騒がしい時間を忘れてしまったかのようだった。 「で、今度は誰に告白されたの? 返事は?」 夕焼けの教室の中、私が沈黙を破る。 毎回おなじみの会話。月に何回か、明子への告白待ちの放課後。 その時間、私は何時も明子がその中の一人に「うん」と言う答えを出すのではないのかと気が気でない。 今日もその『告白待ちの放課後』だった。 そんな不安と好奇心、勇気と言う文字を並べて毎回同じ質問をする。 「返事? 返事なんて何時も一緒、ノーだから!」 そう言って明子はまたカタリと音を立てて立ち上がった。 「じゃ、帰ろうか? いつも待たしちゃってごめんね」 何時もの同じ言葉を明子は繰り返す。 今日も同じ日のように思っていた。 だが、私の中の明子への思いが日に日に強くなっていたのを自分でも感じていた。 今日は何の変哲も無い日になる筈だった。 私の一言・・・その言葉が無ければ。 「私・・・もう無理」 静かな教室の中、私の声が微かに響く。 「え?」 明子のその一言ではっと我に返った。 立ち上がっていた明子は私の方へその白い顔を近づけた。 ふっと影が出来たかと思うと目の前に明子の顔があった。 「ねぇ・・・無理って何が? 私、何か悪い事した?」 そう呟きながら明子が私を覗き込む。 雨の中で捨てられて誰かが拾ってくれるのを待っている子犬のような潤んだ目。 そんなイメージをふっと思い出した。 「唯・・・ねぇ・・・唯・・・私・・・」 そう明子が不安そうな目をしながら呟く。 「ごめん、さっきの言葉何でもないから忘れてね。さ、帰ろ? もう門閉まっちゃうよ?」 私は早く帰りたかった。 この場から早く立ち去りたかった。 先程自分で話した言葉を有耶無耶にしたかった。 流したかった。 消してしまいたかった。 だが、そんな事は無理だった。 「忘れるって? 無理って何が?」 帰ろうとする私の腕を明子が掴んだ。 細く白い手が私の腕にがっちりと絡んで動かない。 繋がった手から明子の温もりがほんのりと伝わる。 私の言った言葉は消せなかった。 私の放った言葉が明子の頭に特に強く残ったようだった。 明子が絡ませた手に強い意志が感じられた。 「痛っ・・・」 「ごめん!」 その言葉と同時に明子の手が離れた。 私の肌にまだ明子の温かさが残っている。 離れてしまった肌に残るのは明子の熱。 「唯、何が無理なの? 私が・・・いつも唯を待たせちゃってるから?」 そう言いながら、明子が私の手を握り締めた。 明子の熱が私の両手にゆっくりと伝わる。 お互いの熱が伝わりきった頃、私はずっと思っていた言葉を口にした。 「明子を誰にも渡したくないの・・・」 それは生まれてはじめての告白だった。 明子に対する思いが一つの言葉になって出てしまった。 それは、明子と中学校の時に出会って今までの5年間はじめて出た言葉だった。 赤く染まる教室に二人で立ち尽くしてた。 頭の中が先程自分で口にした『告白』の言葉でいっぱいになっていた。 |